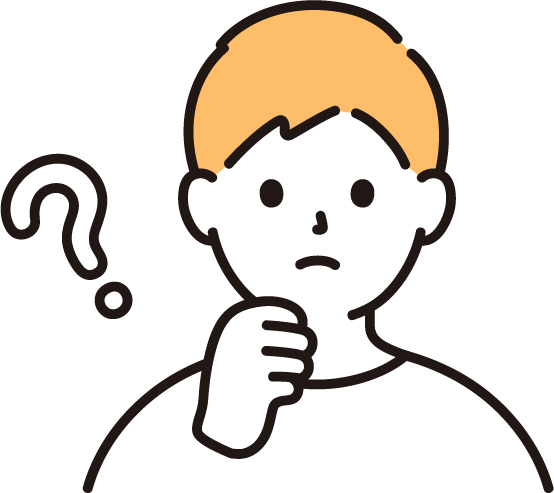
・忙しくて保険金の請求をしないまま数年過ぎてしまった。
保険金はもう貰えないの?
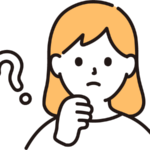
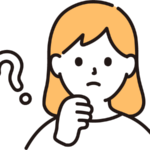
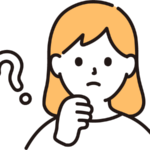
・保険の存在を忘れていて、保険金の請求を長い間していなかった。
もう手遅れ?
入院や手術などをしたにも関わらず、保険金を受け取れなかったら、何のために保険に入っているか分かりませんよね。
しかし実際、保険金を受け取れるのに保険金の請求を忘れている人は数多くいます。
- 入院から退院などの手続きだけでも手間や心理的負担がかかり、保険のことまで意識がいかない
- 面倒な保険のことを後回しにしてしまい、月日が経ってしまった
そのような、過去に保険金を請求し忘れてしまったものは、保険金の受け取りを諦めるしかないのでしょうか。



結論から言うと、ほとんどの場合、請求し忘れていただけであれば
保険会社は対応してくれます。
保険金の請求権について調べると、保険法や約款に「時効」という難しい言葉が並んでいますが、基本的には気にしなくて構いません。
証明書類などが用意できれば、多くの場合、保険金を受け取ることが可能です。
なぜなら、生命保険会社としては、お客さまの保険期間内に起きた不幸(入院や手術など)については、きちんと保障したい(保障すべき)というスタンスがほとんどだからです。
せっかく高い保険料を払い保険をかけてきたのであれば、保険金はしっかり受け取りましょう。
この記事では、生命保険会社の査定部門(保険金をお支払い可能か審査する部署)に10年以上勤務している筆者が、実体験をベースに保険に関する疑問などについて解説します。
営業の部署でないため、保険を売る目的はありません。
中立的な立場で保険の疑問についてお答えしていきます。
数年前の保険金の請求を忘れているケースは意外と多い


私は10年以上生命保険会社の査定部門で働いていますが、意外と数年前の死亡や入院の請求を受け付けることが多いです。



実際に、平成10年に亡くなった方の死亡保険金請求を、
令和7年に受け付け、支払ったこともあります(27年前!)。
特に死亡保険金のように、当事者(被保険者)と保険金の受取人が別人のケースでは
- 「被保険者が死亡(入院)した事実を知らなかった」
- 「自身が保険金を受け取れることを知らなかった」
という理由で、請求がされないまま時間が過ぎてしまったケースが多いのです。
お客さまが何を契機に請求可能な保険金があることを知ったかは会社は分かりません。
生命保険会社としては、お客さまの請求もれを防ぐために、通知や聞き取りなどのアフターフォローを行っていますが、せっかく受け取れる保険金を請求しないままでいる方はたくさんいるはずです。
保険金の請求期限と時効の仕組み


保険金の請求を長い期間忘れているお客さまが、一定数存在するということは知っていただけたでしょうか。
次は保険金の請求期限について解説します。
保険金の請求期限は無限にあるわけではなく、法律や約款で基本的な考え方が示されているのです。
保険金請求の時効は基本的に3年
保険金の請求期限については、保険法第95条や約款(契約した保険の契約書のようなもの。契約時に配布されているかネットで閲覧可能)に以下のように定められています。
- 保険法第95条
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 - 各生命保険会社の約款
多くの保険会社が保険法に基づき、約款で保険金請求の期限を「支払事由が生じた日の翌日から3年以内」と定めています。
※かんぽ生命は特例で5年
なお、時効の起算となる日は「請求権が発生する事由(死亡、入院、手術など)の発生日、またはその翌日」が一般的な考え方となっています。
ほとんどの場合3年を超えても請求できる理由
保険法や約款で3年と時効を定めていても、次の理由から保険金の請求は可能です。
- 自動的に権利が消滅するわけではないから
- 保険会社が時効を成立させるには「時効の援用」が必要だから
- 生命保険会社が「時効の援用」をすることは稀だから
自動的に権利が消滅するわけではないから
法律上の時効は3年と定められていますが、3年経ったら自動的に権利が無くなるわけではありません。
勘違いしやすいですが、3年を経過したからといって保険金等が自動的に受け取れなくなるわけではないのです。
保険会社が時効を成立させるには「時効の援用」が必要だから
「時効」は、時効が成立することによって利益を得られる者(生命保険会社)が、利益を失う者(契約者(保険金受取人)など)に意思表示をして成立します。これを専門用語で「時効の援用」と言います。
保険会社が保険金の支払いを免れるには、「時効になったので、保険金を払わず利益を得ます」という意思表示を、契約者(保険金受取人)などにしておかなければならないということです。
生命保険会社が「時効の援用」をすることは稀だから
生命保険会社としては、正当な受取権があるものは、きちんと保障すべきだと考えています。
自殺や保険金詐欺の疑いがある場合など、事件性が高い場合には時効の援用をする場合が稀にありますが、一部の生命保険会社では公式サイトで「必要書類がそろっていれば請求できる」と明記しています。
生命保険会社はお客さまに保険金を支払いたい!?


生命保険会社で働く社員として、実際のところ時効などの請求期限を意識して仕事はしていません。
私たち保険金の審査(査定)をする社員は、支払いたい、支払いたくないという想いはなく、お客さまの保険事故(死亡や入院)が規定や契約の保障内容に沿った内容かを審査しているだけです。
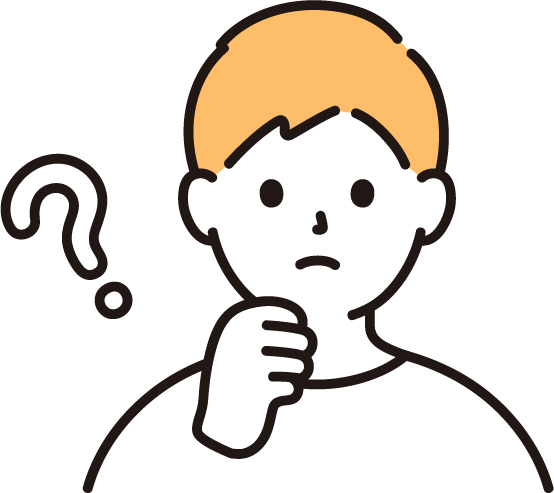
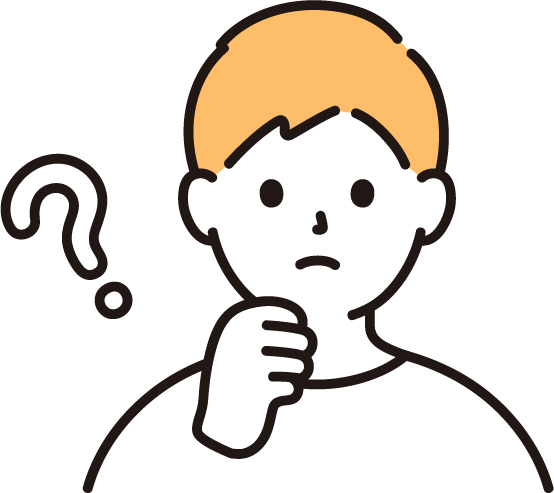
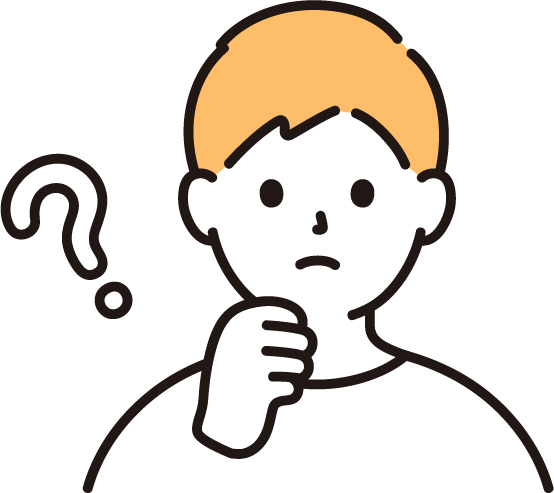
じゃあ、規定にバッチリと当てはまらない、
微妙なものがあったらどうするの。
多くの生命保険会社では、会社がリスクを飲み、保険金をお支払いすると思います。
生命保険会社は何千・何万という契約を保有しています。
そのうちの1件について、支払わないことによるリスクやコスト(お客さまの苦情や、苦情などに対する対応など)を考えた場合、それなりの理由をつけて、保険金を支払ってしまった方が全体的に良いと判断することは珍しくないです。
したがって時効についても、時効を完成させる手間やコストなどを掛けるよりも、そもそもの保険の役割と照らし合わせ、結果として保険金を支払ってしまった方が生命保険会社としても得だと考えているということです。
請求を忘れたときに最初に確認すべきこと
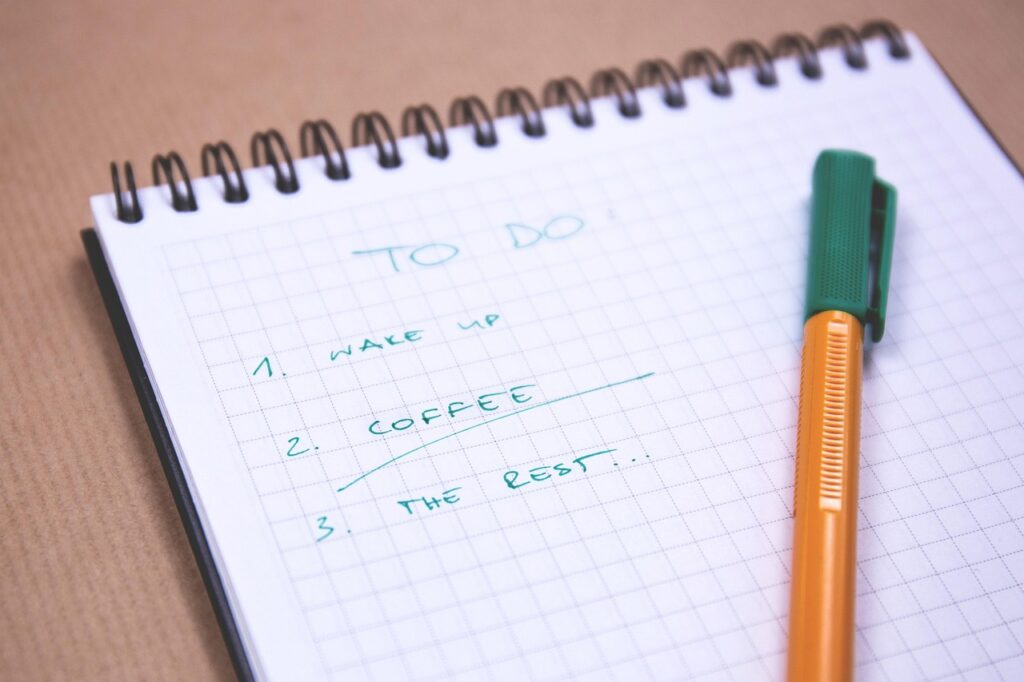
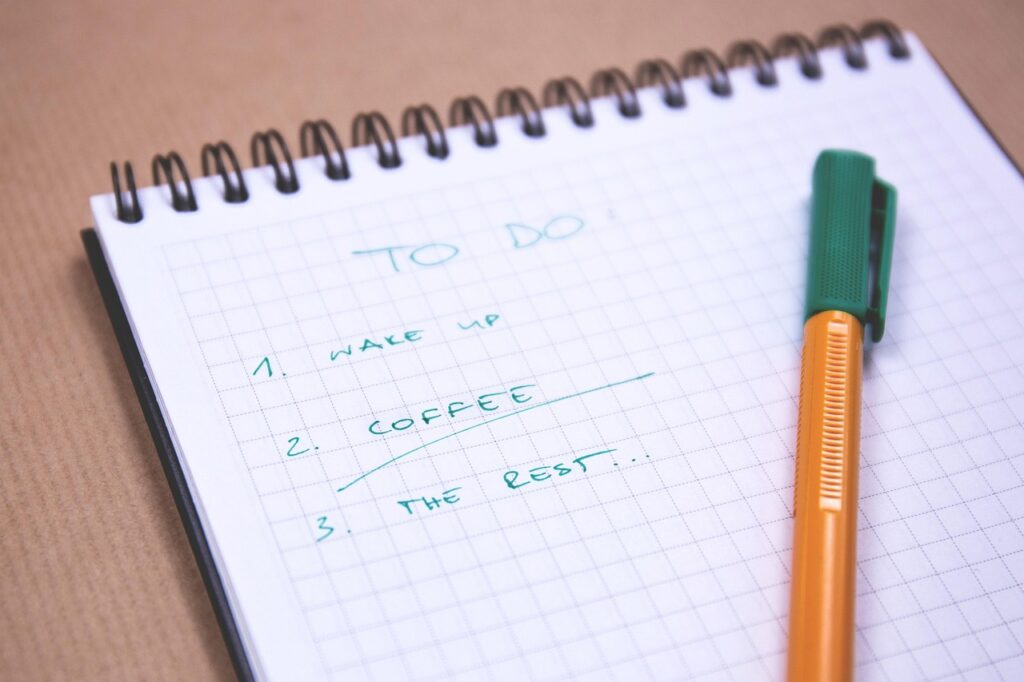
基本的には時効は関係なく、いつでも請求は可能と説明しましたが、実際に請求して保険金を受け取れるかは契約している保険の種類などによって変わります。
事前に確認しておくべき点についてまとめましたので、保障の内容や保険会社の対応、保険事故の詳細に付いて把握しておきましょう。
- 保険の種類および保障内容
- 加入している保険会社の対応方針
- 入院や手術などの実施日
保険の種類および保障内容
自身の契約していた保険が、保険事故(死亡や入院など)を保障するものかは前もって確認しておきましょう。
下記のように保険の保障内容を勘違いしていては、いくら請求するのに期限がないとは言え、保障対象外の場合は支払われませんので注意してください。
- 入院したが、保険は死亡した場合しか保障されていなかった
- 外来で手術を受けたが、保険は入院時の手術しか保障していなかった
保障対象であることが確認できたら、もう少し詳細に、保険金が支払われる可能性があるか確認してみましょう。
保険の契約の内容によっては「◯日未満の入院は対象外」となっていたり、保険は契約していたけれども実は失効しており、入院期間中は失効していたなど、保険金が支払われないケースもあります。
保障の内容は、保険証券などで確認できます。
自分で判断することが難しければ、生命保険会社に電話で問い合わせてみると、支払える見込みがあるか回答してくれます。
加入している保険会社の対応方針
各生命保険会社の公式サイトでは、請求期限について「よくある質問」などで回答していることが多いので確認してみましょう。
基本的には「請求期限を超えていても認められるケースがあるので、請求してみて下さい」という主旨の記載があるはずです。
請求できないのであれば「請求できません」と書くべきなので、認められるケースがあるということは、多くの場合に認められると読み替えて問題ありません。
入院や手術などの実施日
請求することを忘れていたということは、入院などをした日は随分と過去のことになっていると思います。
保険金を請求するには、入院などの保険事故があったことを証明する証明書類(領収書なども含む)が必要です。
病院に証明書類の再発行を依頼する際や、生命保険会社に「いつのことですか」と問われた際に、慌てないよう、いつ頃入院などをしたかは事前に確認しておくとよいでしょう。
保険金を請求する際の対応方法


保障内容を確認し、保険金を受け取れる見込みがあると分かったら、請求の手続きを行います。
詳細は各生命保険会社のHPや、直接保険会社のお問い合わせ窓口に電話などで聞いてみるのが一番早いです。
昔と違い、各生命保険会社で様々な請求方法を取り入れているので、自身の生活スタイルなどにあった方法で対応すると良いでしょう。
保険会社へ請求方法などを問い合わせる
支払える見込みがあると分かったら、生命保険会社の公式サイトなどから、問い合わせ用の電話番号を調べ、電話をかけてみてください。保険金請求の意思があることを伝え、どのように請求すればよいか聞きましょう。
また電話をかけた際に、保険金が支払われる見込みがあるか聞いてみてもよいです。
ただし、生命保険会社の方から電話の段階で「3年を経過しているので請求できない」などと言われたら注意が必要です。
保険会社が時効を理由に保険金を支払わないとするには、事前に契約者などに意思表示が必要だからです。
仮に請求期限を理由に請求はできないと言われても、こちら側から「請求したい」と明確に伝えれば請求は可能ですので、不安がらずにこちらの考えを主張してみてください。
所定の方法で請求する
請求方法は生命保険会社により様々で、以下のような方法が考えられます。
会社によっては対応できない方法もあるので、基本的には案内された方法に従うことになります。
- 必要書類を郵送でやりとりする
生命保険会社から様式等が送られてきて、必要事項の記入や必要書類を同封し、返信用封筒で返送する. - 代理店や各窓口を案内され、実際に足を運んで請求手続きを行う
- インターネットで請求手続きを行う
- 電話で請求を受け付けてもらう
複数の請求方法がある場合、自身でどの方法で請求するか決める必要があります。
手間や安心感を考え、自分に合った請求の仕方を考えてみてください。
請求おいて分からないことが出てきたら、窓口であれば担当者に、それ以外であれば再び電話するなどすれば丁寧に対応してくれます。
保険金の請求に必要な書類


実際に保険金を請求するには、各種証明書類が必要となります。
入院などの事実があったことを証明する医療機関発行の書類と、誰が請求しているか確認するための本人確認書類は必須です。
領収書などの医療機関発行の書類は、昔であれば紛失している方も多いでしょう。
病院によっては領収書の再発行や、保険金請求で使用できる証明書類を別に発行してくれるところもあるようなので、諦めずに根気強く対応しましょう。
診断書や領収書などの病院発行の証明書類
保険金を請求するには、保険事故(入院や死亡など)を客観的に証明する書類が必要です。
いくら自分で「◯日間入院した」と言っても、それを証明する書類がなければ、生命保険会社としては、詐欺が疑われるため保険金をお支払いすることはできません。
保険事故(入院や死亡)を証明する書類は複数あります。
- 診断書(証明書)
- 領収書
- 診療明細書
- 退院証明書
上記の中で、診断書(証明書)を準備するのが一番理想的ではあります。
理由は、診断書(証明書)は領収書などと違い、何の病気で入院や手術などして、どの期間入院したか、何が原因であったかなどの詳細が記載されているため、生命保険会社としては全ての情報をもって審査が可能だからです。
しかし診断書は、基本的に取得するには費用が発生します。
なるべく負担を減らしたいのであれば、退院時などに無料で発行される、領収書や診療明細書を利用して請求ができないか生命保険会社に確認してみましょう。
領収書などで請求を受け付けられる基準は、生命保険会社によって違います。
昔に比べ生命保険会社は、お客さまの負担をなるべく減らし、請求漏れを防ぎたいなどの観点から、診断書(証明書)ではなく領収書などを利用して請求できる範囲は拡大しています。
マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類
保険に限らず、何か手続きするには本人確認書類は必須です。
多くの場合、写真が付いているマイナンバーカードや運転免許証を提出すれば問題ありません。
保険金の請求手続きを、他人に依頼する(委任する)場合は、依頼される側の本人確認書類も必要となります。
書類の入手方法と注意点
領収書などが手元になければ病院などに発行を依頼することになりますが、基本的に病院の領収書は再発行不可とされています。
再発行不可のため必要書類が揃わず保険金の請求ができないと思いがちですが、病院によっては領収書の再発行を認めてくれるケースもありますので、諦めずに病院に問い合わせてください。
また仮に領収書の再発行の対応ができなくとも、病院側が別の形式で証明書類を発行してくれるはずです。
生命保険会社には「領収書が必要」と言われるかもしれませんが、病院が発行した証明書類であれば基本的に対応可能ですので、不安であればもう一度生命保険会社に問い合わせるなどして証明書類を準備しましょう。
トラブル・失敗事例とその回避方法


査定経験10年超の経験から、よくあるミスや、事前にトラブルを避ける方法を紹介します。
基本的な保障の内容を把握していればほとんど防げますので、不要な手間をかけないようきちんと確認しておきましょう。
よくある請求ミス(勘違い)
ちょっとした勘違いにより、支払えないことや、請求後に保険会社から書類の追加提出を依頼されることがあります。



保険金が支払われないにも関わらず、必要書類の準備などに時間を使っては非常にもったいないです。
どのケースにおいても、事前にきちんと確認する、もしくは生命保険会社に電話などで問い合わせれば分かることなので、不安な点は解消してから請求しましょう。
- そもそも保障がない(死亡保障しかない契約なのに入院保険金を請求)
- 保険金の受取人が違う
そもそも保障がない(死亡保障しかない契約なのに入院保険金を請求など)
意外と勘違いしていることが多いのがこのケースです。
昔保険に入っていて、保障の見直しなどをしていない状態だと「保障されているものだと思っていた」と勘違いして請求してしまう場合があります。
受取人だと証明する書類の不足
本来の受取人が亡くなってしまい、自身が相続人として保険金を受け取ることができるケースについても注意が必要です。
相続人などで保険金を受け取る際は、自分が相続人であること(誰が相続人であるか)の証明と、自分以外の他の相続人に同意を得る必要があります。
亡くなった親が受け取れるはずだった保険金があることが分かり、相続人として受け取る際には、戸籍謄本などの書類が追加で必要となります。
戸籍謄本は取得範囲が広いと、総枚数が数十枚にもなることもあるため、抜け漏れのないよう確認が必要です。
保険会社から万が一拒否された場合の対応策
仮に生命保険会社から、請求期限を理由に請求できないと言われても、まずは「請求できるはず」と主張してみてください。
問い合わせを受ける保険会社の方も人間ですので、勘違いして、こちらの意図が伝わっておらず誤った回答をすることもあります。
一度断られた場合でも「請求できるはず」「他の生命保険会社では請求できるらしい」と強く伝えてみましょう。
請求忘れを防ぐための習慣と対策
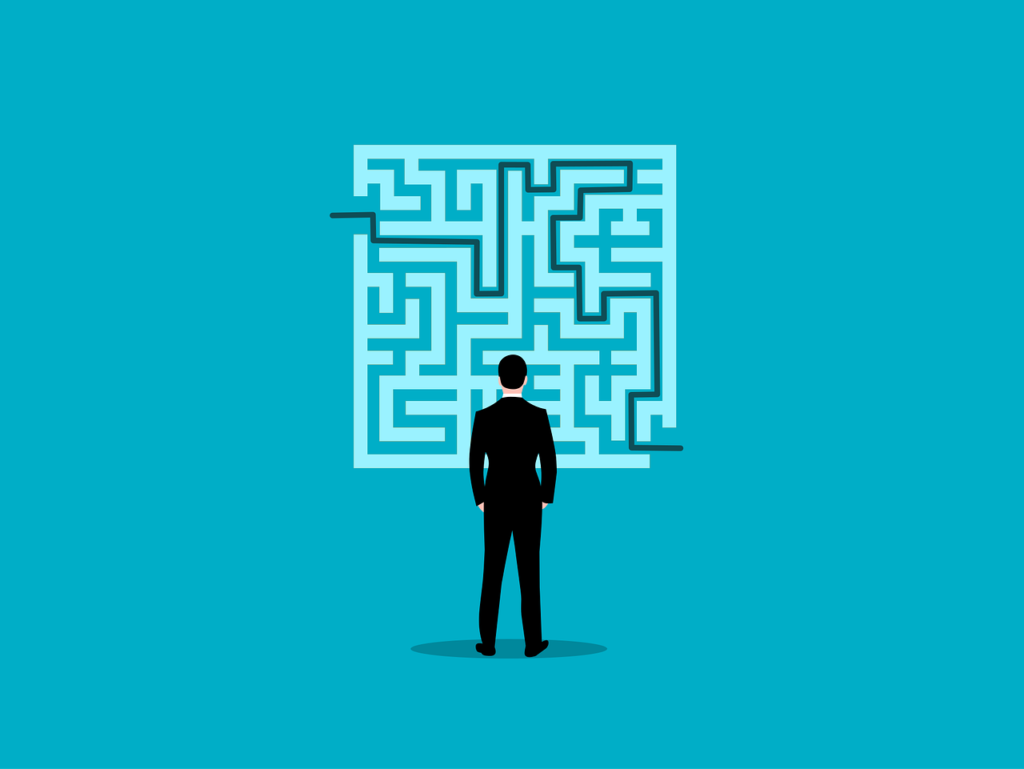
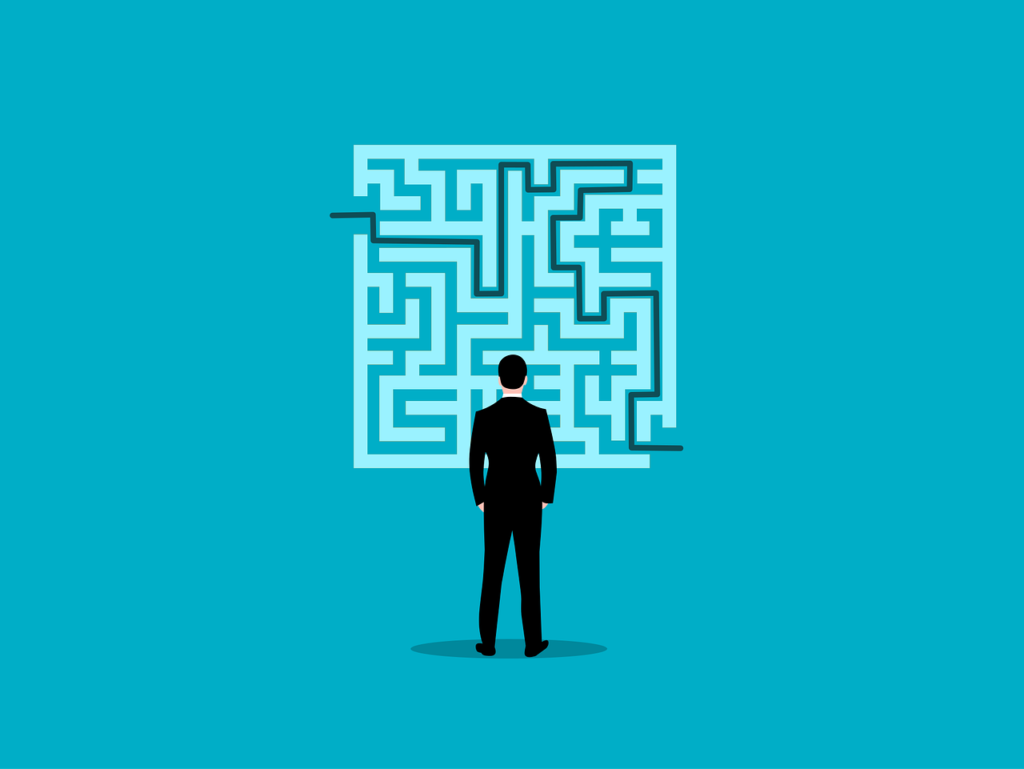
生命保険は保険料を毎月払っているものの、日常使う場面がほとんどありません。
使う場面がない方が幸せです。
とはいえ、いざとなったときに必要となるのが保険です。
基本的に請求忘れを防ぐには、自分の契約している保険では何が保障されるのか、定期的に見直すことしか対策はないです。
「毎年◯月に見直す」「家族(または信頼できる人)と見直す」など、自分のルールを定めておくとよいでしょう。
定期的な保障の見直し
生命保険は契約した当初は、保障内容などは覚えているものの、数年経ったら忘れてしまうのが普通だと思います。
保険の出番は「何か起きた時」なので、日々何事も起きず生活できていれば、保険のことなど忘れてしまって当然です。
ただいざとなった場合に備えて、自分がどのように保険に入っているかは頭の中に留めておきたいものです。
自身で見直す場合は、会社員であれば毎年10月頃に年末調整の申請をするはずなので、生命保険料控除を申請する際に、保障内容などについて軽くおさらいしておくのが良いと思います。
他の人に頼るならば、契約している生命保険会社への問い合わせや、FPなどに相談するのが良いでしょう。
他人に保障の見直しを依頼する場合は、余計な保険などを勧誘される可能性があるので注意してください。
家族との情報共有
家族と保険のことについて話す機会があれば、自身のそして家族の保険加入状況がそれぞれ分かるため、何かあった際に保険金の受け取り漏れを防ぐことができるでしょう。
しかし家族と保険のこと、つまりお金の話をすることに抵抗がある人も多いでしょう。
無理に話をして家族との関係が悪くなってしまっては元も子もないので、家族と共有する際は慎重に進めた方がよいです。
よくある質問(FAQ)


時効を過ぎたら一切ダメ?
保険会社によって対応は違う?
- 保険会社によって対応は違うの?
-
必要書類などは違う可能性があります。
時効を過ぎても請求できる点は、ほとんどの生命保険会社は変わらないと思いますが、請求に必要な書類などは各会社で違う可能性はあります。
A社では領収書で請求できたが、B社では診断書の提出を求められるケースがあるかもしれません。
基準は生命保険会社によるので、基本的にはその会社の取り扱いに合わせるしかありません。
自費診療は対象になる?
- 自費診療は保険金の支払対象になる?
-
自費診療は対象とならないことがほとんどです。
保険はあくまでも、入院・手術など医師の管理下において治療を受ける必要があったと判断された際に保障を受けられるものです。
自身で必要と思ったからという理由で受けた手術などは、当然ながら保障されません。
(保障したら保険会社が破産してしまいます。)
まとめ:請求期限を過ぎても保証期間内なら対応可能


生命保険の保険金請求には「3年の時効」というルールがありますが、実際には多くの生命保険会社は時効を主張せず、必要な書類がそろっていれば支払いに応じてくれるケースが大半です。
「もう期限を過ぎたからダメだ」と自己判断してしまうのではなく、まずは契約している保険会社に連絡してみましょう。
ただし、保障対象外の内容であったり、必要書類が揃わなかったりすると支払いに進めない可能性もあります。
診断書や領収書などの証明書類、そして本人確認書類をしっかり準備することがスムーズな請求につながります。
また、年に1回の保障内容の確認や、家族との情報共有を習慣化して、そもそもの「請求忘れ」を防ぐことも大切です。
せっかく長年保険料を払ってきたのですから、受け取れる保険金はきちんと請求して生活に役立てましょう。
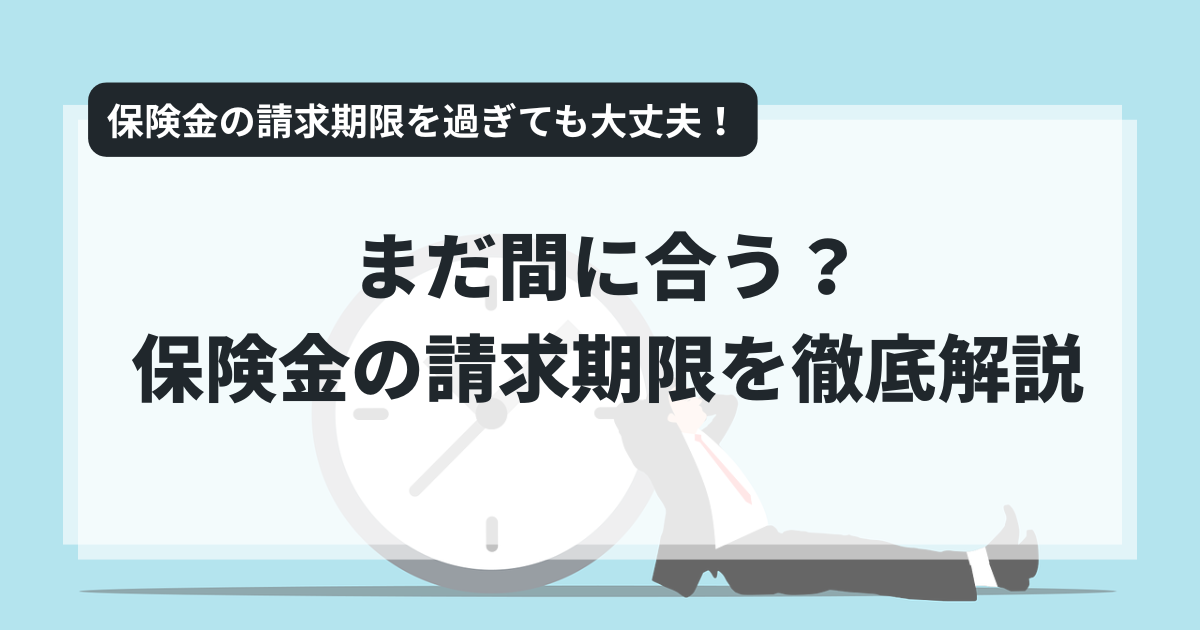
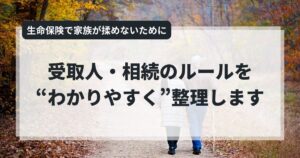
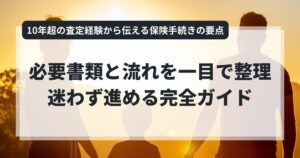
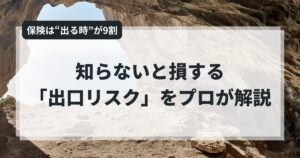
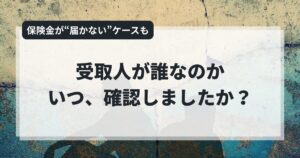
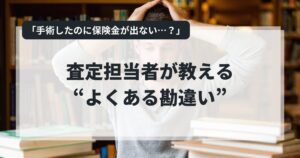
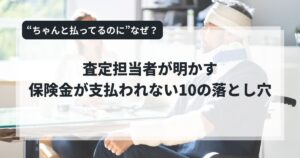
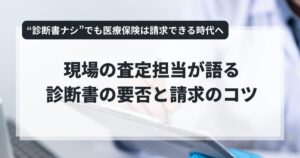
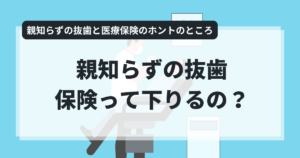
コメント