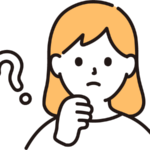
「ちゃんと保険料を払ってきたのに、いざという時に保険金が下りないなんて…」
そんな不安や疑問を感じたことはありませんか?
保険は「もしものときの安心」のはずなのに、いざ請求してみると「支払われません」と言われるケースがあります。
その理由の多くは、契約内容の誤解や、書類・手続きのちょっとしたミスです。
この記事では、**生命保険会社の査定担当者が実際に見てきた「支払われない10のケース」**を、実例を交えてわかりやすく解説します。
- なぜ支払われないのか、その「本当の理由」
- 自分や家族が同じ失敗を防ぐためのポイント
- 確実に保険金を受け取るための準備すべきこと
保険金請求トラブルのほとんどは、“知っていれば防げる”ものです。
10年以上の査定経験から見えてきた「支払われない落とし穴」を知り、あなたとご家族の大切な保障を、しっかり守っていきましょう。
保険金が支払われない主な理由【実例10選】
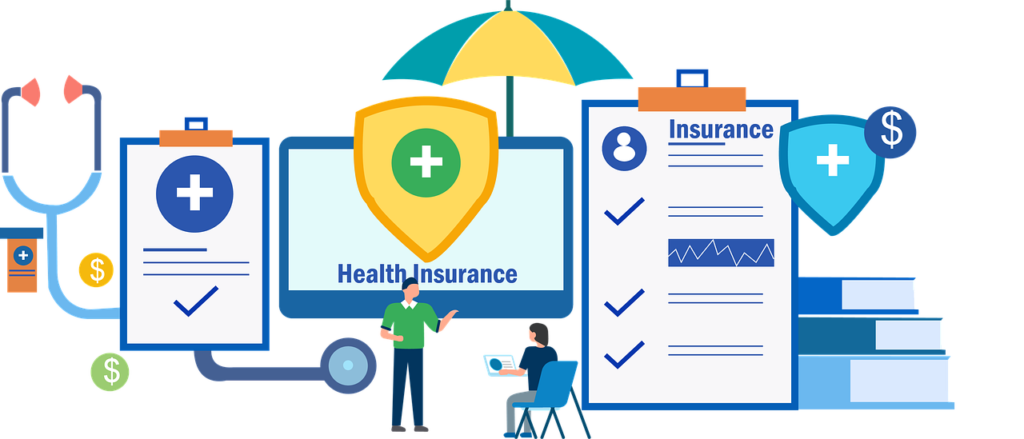
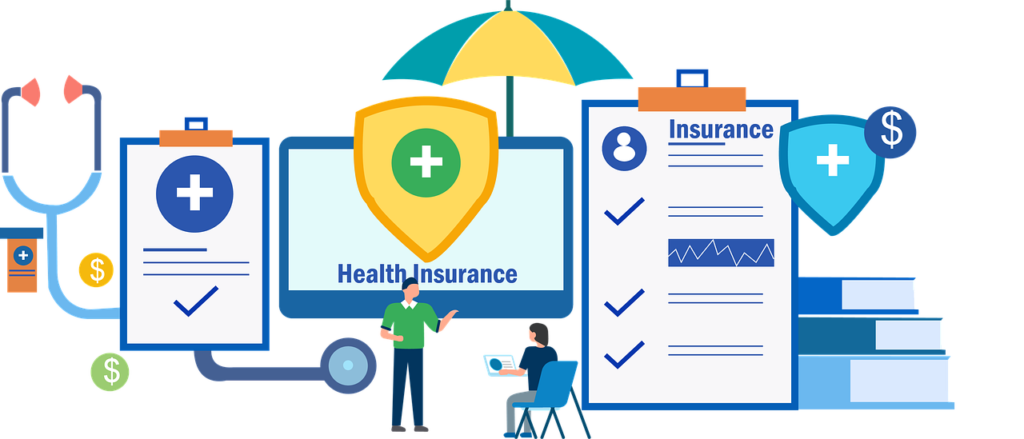
「ちゃんと保険料を払ってきたのに、いざという時に保険金が下りない。」
そんな声を、私は査定担当として何度も耳にしてきました。
しかし実際は、契約内容の誤解や、書類や告知のちょっとしたミスなど「支払われないのには必ず理由」があります。
ここでは、保険金が支払われない主な10のケースを、現場でよく見かけた実例を交えながら解説します。
下記のケースに当てはまっていないか確かめてみてください。
① 契約上の支払対象外だったケース
保険金が支払われない理由のもっとも多いケースが「契約内容の勘違い」です。
たとえば、医療保険で「手術をしたから手術給付金がもらえる」と思っていたのに、実際にはその手術が「給付金対象外の処置」だったというケースがあります。
- 日帰りで行う簡易的な内視鏡処置をした
- 「レーザー焼灼」「切開」など、医師の説明では“手術”と呼ばれていても、約款上では「対象外」とされている
まず手術かどうかの判断ですが、保険会社では「日本医師会の手術分類表」などをもとに、手術コードや内容を照合して支払可否を判断します。
そのため、医師が「手術をした」と言ったとしても、実際に施行した「手術名」「保険の定義」の方が支払査定時には重視されるのです。
確認する方法としては、病院から発行される領収書の手術点数欄に点数が入っていれば、少なくとも「手術」であったといえるでしょう(「処置」ではないと言える)。
あとは施行した手術が、契約している保険で保障されているかどうかで、保険金が支払われるかが決まります。
契約時に「どの範囲まで対象になるか」を確認することが大切です。
古い契約では、今の医療制度に合わない内容のままになっている場合もあります。
たとえば昔の契約は、「入院は◯日以上から支払い」や「内視鏡による手術は対象外」など、現在販売している契約より支払要件が厳しい傾向にあります。
心配なときは、一度保険会社に保障内容について問い合わせてみましょう。
② 免責期間中の発症だったケース
がん保険などでよくあるのが、「免責期間(めんせききかん)」による支払対象外です。
多くのがん保険では、加入後すぐに病気が見つかった場合、「契約から90日以内の発症は支払われません」というルールがあります。
加入してから2か月後にがんが見つかり、「せっかく保険に入ったのに支払われないの?」と不満を感じた契約者の方がいました。
約款上では「90日経過後の診断確定」が条件でした。
これは加入前から、がんが進行していた可能性を排除するための仕組みです。
査定現場では、診断書の日付と契約日を照らし合わせ、「発症日(症状の初発日)」を特に重視します。
がんの場合、「初めて異常を指摘された日」や「精密検査を受けた日」が鍵になることもあります。
契約内容を確認して、どの保険にどのような「免責期間」が設定されているかを把握しておきましょう。
特に新しく保険に入り直した場合は注意が必要です。
加入してから短期間で病気が見つかると、「前の保険なら出たのに…」という後悔につながることもあります。
③ 告知義務違反と判断されたケース
告知義務違反は保険金が支払われるかどうかだけでなく、契約の存続にも関わるためトラブルになりやすいケースのひとつです。
保険加入時に「過去3年以内に通院や投薬はありますか?」などの質問に対して、「もう治ったから」「軽い風邪だったから」という理由で申告しなかった場合、“告知義務違反”と判断されることがあります。
1年前に高血圧で通院していた方が、申告せずに保険に加入したケース。
脳梗塞で保険金を請求したところ、「加入時の告知内容に虚偽があった」として支払いが拒否されました。
更に保険契約そのもの自体も、嘘の申告をしていたことから、告知義務違反による契約解除となりました。
ただし、ここにはグレーな部分もあります。
意図的に隠していたのか、それとも「本人が軽いと思っていた」かの違いで、査定判断が分かれることもあります。
査定や契約審査の現場では、「告知義務違反=即契約解除」ではなく、以下の点を確認のうえ判断します。
- 故意または過失によるものか
- その事実が保険金支払いに影響したか
多くの場合、契約者の同意を得たうえで、調査部門が医療機関に診療記録を取り寄せたり、保険募集をした社員に保険加入時の状況について確認します。
保険加入時の告知は、ありのままに事実を述べることが鉄則です。
たとえ保険契約時に意図的に申告をしなかったとしても、医療情報は必ず記録が残るため、後で発覚した場合のほうがリスクが高くなります。
告知内容に迷った際は「少しでも心配なら書いておく」方が良いです。告知は正直に行いましょう。
④ 診断書の記載内容が基準を満たしていなかったケース
意外と多いのが「診断書の内容が不十分だったために支払いが見送られるケース」です。
診断書は保険金を支払ううえで最も重要な書類ですが、医療機関のミスで必要な日付や病名が抜けていたりすることがあります。
ただしこのケースは、医療機関に追記・訂正を求めることで問題が解消され、結果として保険金が支払われるものが多いです。
提出された入院証明書に、医師氏名が記入されていなかったため、査定が保留になってしまった。
後日、医師に追記してもらい、無事に支払いとなった。
査定では、診断書について以下の3点を特に注意しています。
- 診断名が確定しているか
- 診断日(または手術日・入院日)が明記され矛盾がないか
- 医師の署名・押印があるか
このどれかが欠けていると、支払可否を判断できず保留になります。
- 医師に診断書を依頼する際、「保険会社への提出用」と伝える
- 診断書が出来上がったら、病名や診断内容(手術日など自分がわかる範囲)、医師の署名などの記載を確認する
- コピーを取っておく(後で見直すため)



診断書の内容は、一般の方には確認しづらい部分ですが、提出前に一度“日付と病名”だけでもチェックするだけでトラブルを減らせます。
⑤ 保険金請求書類に不備があったケース
「支払われない」というより「支払いが進まない」ケースの多くが、書類不備です。
保険会社は、提出書類がすべて揃って初めて査定に入ります。
どこか1箇所でも不備があると、確認や再提出に時間がかかり、結果的に支払いが遅れてしまいます。
- 請求書の署名・押印漏れ
- 口座名義が契約者と異なる(例:旧姓のまま)
- 医療証明書や領収書のコピーが足りない
- 本人確認書類の有効期限が切れている
査定担当者は、書類の内容よりもまず「形式的要件」をチェックします。
書類が揃っていない場合は、査定そのものが中断されます。不備を解消しなければ査定が進まないのです。
特に口座情報やマイナンバー関連の不備は、支払業務上のトラブル防止のため慎重に扱われます。
- 郵送の場合、同封されている「チェックリスト」などを使う
- 郵送ではなく、可能なら窓口・オンラインでの請求も検討する
- 不安な点があれば、保険会社のお問い合わせ先に連絡する
ちょっとした記入ミスが原因で、支払いが1〜2週間遅れることも珍しくありません。
仮に「ミスをしてしまったかも」と思ったとしても、焦らず「保険会社からの不備連絡メールや郵送通知」を確認し、粛々と対応しましょう。
⑥ 受取人の指定に問題があったケース
これは死亡保険金の請求で特に多いトラブルです。
「受取人が亡くなっていた」「離婚したのに名義変更していない」など、契約時の情報が古いままになっているケースがあります。
夫が亡くなり、妻が保険金を請求したところ、契約書上の受取人が婚姻前の状態である“夫の母(既に亡くなっている)”のままになっていた。
この場合、保険会社は法定相続人の確認が必要となり、戸籍謄本や遺産分割協議書などの提出を求めるため、支払いまでに時間がかかります。
査定担当は、死亡保険金の支払前に必ず「戸籍・相続関係図」を確認します。
受取人が死亡している場合は、約款や民法上の相続ルールに従い、“正当な受取人(相続人など)”に支払わなければなりません。
受取権がない方に保険金をお支払いすることは絶対に避けなければならないため、本人確認書類や戸籍謄本の提出を求めることになります。
- 結婚・離婚・出産・家族の死亡など、ライフイベント時は必ず受取人を見直す
- 保険証券やマイページで受取人の名前を確認しておく
- 万が一、指定が曖昧な場合はFPや保険会社に早めに相談
受取人の指定は生前にしか変更できません。
残された家族などのためにも、今しかできない確認として見直しを怠らないようにしましょう。
⑦ 保険期間がすでに終了していたケース
意外と見落とされがちなのが、契約期間の終了です。
とくに「定期タイプの医療保険」や「養老保険」では、10年・15年などの保険期間が自動的に満期を迎えることがあります。
10年前に加入した医療保険の請求をしたところ、「すでに保険期間が満了しており、契約は終了しています」と言われたケース。
契約者は「自動更新だと思っていた」と話していました。
査定担当は、支払請求を受けるとまず「契約状況(有効・失効・満期)」を確認します。
基本的には保険期間が過ぎている場合、いかなる病気・事故であっても支払対象外です。
ただし、保険期間中に起きた入院や事故であれば、請求時点で期間が過ぎていても、支払対象となることがあります。保険期間が終了する日付を跨ぐような入院であれば、一度保険会社に問い合わせることをおすすめします。
- 契約内容に「満期日」「更新有無」が記載されているか確認する
- 郵送の「更新案内」や「保険料変更通知」は必ずチェックしましょう
- 長期契約が心配な場合は「終身タイプ」の保険を検討する
「ずっと続くと思っていた保険が、実は終わっていた」これは査定現場で本当に多い“もったいない支払不能”の原因です。
保険が機能していない場合、ライフプランの見直しも必要となるため、自身がどのようなタイプの保険に加入しているか最低限把握しておきましょう。
⑧ 保険料の未払い・契約失効状態だったケース
「ちゃんと入っているつもりだったのに、実は保険料が引き落とされていなかった」というケースも存在します。
クレジットカードを更新した際に保険会社への登録を忘れ、数か月間引き落としができずに契約が“失効”してしまっていた。
失効していることに気づかず、その後に入院したため、保険金が支払われなかった。
保険は一定期間(通常は2〜3か月)の未払いが続くと契約が「失効」します。
ただし、その後一定期間内(復活期間)に保険料を支払えば、再度契約を有効にできる「復活制度」があります。
保険会社は契約が失効してしまわないよう、念入りに契約者に通知等を行うものですが、保険会社からの通知を放置してしまう方も多いのが実情です。
- 保険料の支払い状況は、マイページや保険会社のアプリで確認できる
- 口座変更・カード更新のときは、保険料の引き落としの設定を怠らない
- 「契約失効通知」が届いたら、すぐに内容を確認し、必要に応じて復活手続きを検討する
保険料を払う意思はあったものの、意図せず「システム変更で止まっていた」ケースも多いため、まずは慌てずに契約状況を確認しましょう。
⑨ 詐欺・虚偽申告の疑いで調査中のケース
これは少し特殊ですが、「支払いが遅れている」ときによくあるのが調査中の状態です。
同じ病気・同じ入院で、複数の保険会社に請求をしているものの、内容に不一致があったため、保険会社が病院に確認を依頼し、調査期間が延びた。
このように、「保険金を出すべきか判断するための確認」が入ると、 “支払保留”状態になることがあります。
査定担当は、不正請求防止のため「医療機関への照会」や「診療記録の確認」を行います。
「正確な判断のための確認」の調査自体は決して珍しいことではありませんが、「不正の疑い」は話が別です。
契約者や病院の不正(保険金詐取)が疑われる場合は、より慎重に判断する必要があるため、調査に時間がかかります。
- 保険会社から「調査中です」と言われたら、焦らず経過を確認する
- 可能なら「調査の目的」「期間の目安」を問い合わせる
- 書類や証拠を求められたら、できるだけ早めに提出
調査期間中に感情的になってしまう方も多いですが、「支払いを正確に行うためのプロセス」であることを理解しておくと安心です。
⑩ 災害・事故の内容が補償対象外だったケース
最後に紹介するのは、そもそも契約の補償範囲に含まれていなかったケースです。
- 地震や津波などの自然災害
- 飲酒運転による事故
- 自殺・自傷行為によるケガ
- 戦争・暴動などの特殊事象
上記は多くの保険で「免責事項(支払対象外)」として明記されています。
免責事項に該当する可能性があると判断した場合、「原因・根拠の確認」が査定では最も重要です。
事故証明書や警察の記録を確認し、免責条項に該当するかを慎重に判断します。
たとえば、飲酒運転や自傷行為が疑われる入院の場合、警察や病院の記録を確認します。
契約者自身に過失があるのか、またそれを保険会社が証明できるのかで、保険金の支払可否が変わってきます。
- 保険証券にある「免責事項」欄を一度読んでみる
- 不安な災害リスク(地震・風水害など)は特約の有無を確認
- 自動車・火災・生命保険など、複数保険の補償範囲を整理しておく
「対象外だった」という結果を防ぐには、 “契約する前に何が守られて何が守られていないのか”を理解することが一番の対策です。
なお、多くの人・地域に被害が及んだ東日本大震災では、約款上その甚大な被害から通常であれば保障対象にできないものですが、保険会社としての責務や社会情勢などを鑑み、ほとんどの生命保険会社が保障することを決めました。
新型コロナウィルスも同様に、被害が大きければ保険会社が保障できず、逆に保険会社の経営が傾く恐れが生じるものですが、免責と思われるものでも例外として保障されたケースもあります。



「支払われない」と聞くと冷たく感じるかもしれませんが、 多くのケースは“契約上のルールに基づいた判断”です。
保険金は“運”ではなく、“きちんとした準備と理解”で受け取れるものです。
支払われなかったときの正しい対処法


「保険金が支払われません」と通知が届いたとき、 多くの人は「ダメだったんだ」と落ち込んでしまいます。
しかし、“支払われない”=“終わり”ではありません。
実は、まだできることがいくつかあります。
大切なのは、「感情的に動かず、正しい順序で確認すること」です。
ここでは、査定担当者の立場から、支払われなかったときに取るべき具体的なステップを順に解説します。
※約款と照らし合わせ、支払われる可能性があることを前提とした場合の対処法です。
正当な理由で保険金が謝絶されたものを、無理やり支払ってもらうよう行動するものではありません。
Step1 「なぜ支払われなかったのか」を正確に確認する
最初にやるべきことは、理由の確認です。
保険会社は支払わない場合、必ず「支払対象外理由」を書面で通知します。
書面には、次のような文言が書かれていることが多いです:
「約款第○条(支払事由)に該当しないため、今回はお支払い対象外と判断いたしました。」
ここで重要なのは、「どの条文」「どの事実」が問題になっているのかを正確に読み取ることです。
たとえば、以下のように原因がわかれば、次の対応方針が明確になります。
- 診断日が契約前だから対象外となった
- 診断書の内容が不足していた
- 約款に支払対象外の手術と明記されていた
査定担当者は「支払えないから拒否する」のではなく、契約内容と診断書の整合性が取れないため支払えないと判断しています。
理由を正確に把握すれば、再提出や異議申立ての道が開けます。
Step2 不明点はそのままにせず、担当者に質問する
「書面を読んでも支払対象外となった理由がよく分からない」場合は、 そのままにせず、保険会社へ直接問い合わせるのが最善です。
- 電話する前に書面で質問内容を整理する
- 「約款のどの部分の記載(条文)を根拠にしているのか」を具体的に聞く
- 担当部署(保険金サービスセンター等)の担当者名を控える
「保険会社に質問するのは気が引ける」という方も多いですが、保険会社にとって“質問される”ことは日常業務です。
遠慮せずに聞いた方が、結果的に早く解決します。
Step3 書類・診断書の再提出や修正を検討する
「記載内容の不足」や「誤り」が原因なら、再提出や修正で支払いに至るケースも少なくありません。
- 医師の診断書に“疑い”と書かれていた → 確定診断書を再提出
- 手術の情報が不足していた → 医師に正式名称で追記を依頼
- 記載誤りがあった → 保険会社から再発行の用紙をもらい再提出
医師も人間なので、診断書の記載誤りはどうしても発生してしまいますし、保険会社は、正式な依頼があれば必ず再確認を行います。
ただし再度査定を実施する場合は、過去に支払われなかった状況から、新たな事実(記載誤りがあったなど)が判明したことが前提です。
過去に保険金が謝絶となったものから、何も状況に変化がなければ、支払対象外という結果は変わりません。
まずは保険会社に、新たな事実が判明した旨と、再度査定する価値があるか問い合わせした方がよいでしょう。
再提出の際は、コピーを必ず手元に残すようにしましょう。
提出後のやりとりをスムーズにするために、控えは非常に重要です。
Step4 それでも納得できないときの最終手段
上記の手順を踏んでも、なお結果に納得できない場合は、**「異議申し立て」や「第三者機関への相談」**という最終的な方法もあります。
とはいえ、これは特殊なケースであり、多くの場合は③までの段階で解決します。
それでも進めたい場合は──
- 保険会社に「異議申し立て書」を請求し、理由を明確に記載する
- 必要があれば、生命保険協会の「生命保険相談所」や「金融ADR(裁判外紛争解決制度)」へ相談
ポイントは、「感情的に戦う」ではなく、「公平な第三者の視点を入れて再確認してもらう」ことです。
異議申し立てが出された場合、査定担当とは別の部署が再確認を行います。
「再審査の仕組み」は、契約者の権利として正式に用意されています。
保険金が支払われないときは、どうしても焦ってしまいますが、正しい順序で動けば、支払いに至るケースも少なくありません。



「怒るより、まず確認」
「疑問はその場で質問」
「書類は丁寧に整える」
この3つを意識するだけで、結果が変わってきます。
トラブルを防ぐために、今できる3つの準備


ここまで見てきたように、保険金が支払われないケースの多くは、“契約の内容”や“手続きのちょっとした行き違い”が原因です。
つまり、正しく理解し、日ごろから準備しておけば防げるトラブルがほとんどなのです。
ここでは、いざというときに困らないための「3つの予防策」をご紹介します。
どれも特別なことではなく、“今日からできること”ばかりです。
契約内容を「年に1回」見直す習慣をつくる
自分がどんな保険に入っているかを定期的に確認すること。これが一番の予防策です。
あなたは自分の契約している保険の内容をパッと言うことができますか。
多くの方は自分の契約内容を正確に覚えていないものです。
たとえば──
- 保険期間が満期を迎えていた
- 受取人の名前が古いままだった
- 特約が外れていた(がん・手術など)
こうした“気づかぬままの状態”が、保険金請求時にトラブルにつながる可能性となるのです。
- 年に1度は保険証券(またはマイページ)をチェック
- ライフイベント(結婚・出産・転職)後は必ず見直す
- 古い契約ほど「満期」「特約の廃止」などに注意する
査定現場では、「契約が失効していた」「特約が外れていた、あると思っていた」ケースが本当に多いです。
“確認の習慣”が何よりの予防策になります。
重要書類は「家族が見つけられる場所」に保管する
請求時に最も困るのが、「どこに書類があるか分からない」という状況です。
とくに、家族が請求する死亡保険や入院保険では、書類の所在が分からず、支払いが大幅に遅れてしまうことがあります。
- 保険証券・診断書・領収書を“ひとつのファイル”にまとめておく
- 家族に「保険の場所と会社名」を共有しておく
- スマホのメモアプリやクラウドに「保険一覧」として保存する
査定担当として、実際に「ご家族が保険を探し出すのに数か月かかった」事例を何度も見ました。
どんなに良い保険でも、“見つけてもらえない”と意味がありません。
「自分がいなくても、家族が迷わず請求できるか」この視点で整理しておくことが、最大の予防策です。
医療・診断書の依頼は「早め・丁寧に」を心がける
保険金請求で「診断書の発行」に時間がかかることもあります。
病院によっては2週間程度かかることもあるため、入院や手術が決まった時点で、早めに医師へ依頼することが大切です。
- 受付で「保険会社提出用の診断書をお願いします」と伝える
- 出来上がったら、病名と診断日だけでも確認しておく
診断書の“記載漏れ”や“記載誤り”が原因で支払いが遅れるケースは発生します。
医師にとって保険書類はあくまで“依頼書類”の一つです。
依頼する側(契約者)としても依頼した内容がきちんと対応されているか、完璧でなくとも確認するようにしましょう。
保険トラブルの多くは、「知らなかった」「準備していなかった」ことから始まります。
- 契約内容を知る
- 書類を整える
- 早めに動く
この3つを意識するだけで、支払われないリスクを大幅に減らすことができます。



保険金請求は“知っている人ほど得をする”世界です。
難しい知識はいりません。
ほんの少しの確認と準備が、「もらえない」を「ちゃんと受け取れる」に変えてくれます。
まとめ:保険金を確実に受け取るために覚えておきたいこと


保険金が支払われないケースには、「契約上の理由」や「書類の不備」など、いくつかのパターンがあります。
しかし、多くのトラブルは“正しい知識”と“早めの行動”で防げるというのが、私が査定担当として10年以上現場を見てきた実感です。
- 契約内容を知っておく
→ 自分の保険が「どんなときに・いくら支払われるのか」を理解する。 - 書類を整えておく
→ 保険証券や診断書、領収書をひとまとめにし、家族にも伝えておく。 - 不安や疑問はすぐ確認する
→ 通知内容や査定結果に疑問があれば、遠慮せず問い合わせる。
この3つを押さえるだけで、「支払われない」を「きちんと受け取れる」に変えられます。
保険金請求は、決して“争い”ではありません。契約者が受け取るべき正当な権利です。
だからこそ、「難しそう」「面倒そう」と感じて放置せず、少しでも早く、確実に動くことが大切です。



「もっと早く相談してくれたら、面倒なことにならなかったのに…」
そう感じた案件を、何度も見てきました。
保険金は、困ったときにあなたを支えるためにあります。
迷ったら一歩踏み出して、確認する勇気を持ってください。

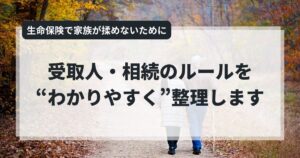
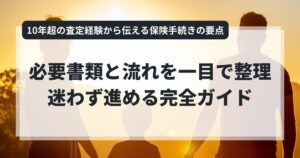
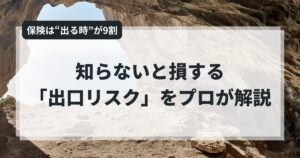
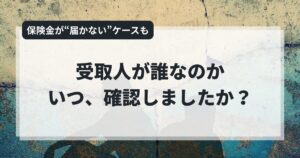
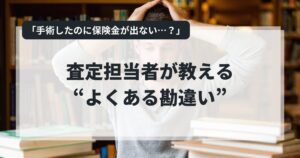
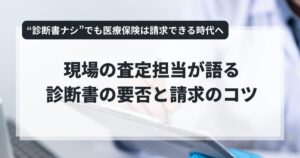
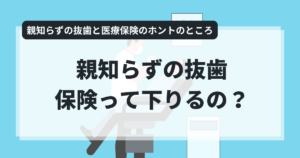
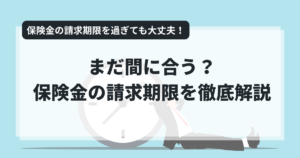
コメント