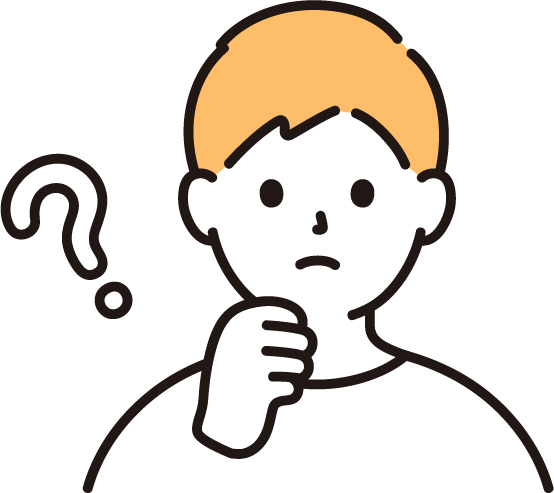
「入院保険金を請求する予定だけど、病院に診断書の発行を依頼した方がいいの?」
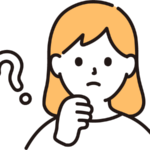
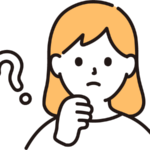
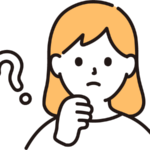
「診断書を発行してもらうのって費用がかかるの?」
一般に保険金の請求は、何度も経験するものではないので、保険金請求と聞くだけで身構えてしまう人も多いでしょう。
せっかく医療保険に入っていたおかげで「入院や手術保険金の給付を受けられる」と思ったとしても、何を準備してどう請求すればいいか不安になりますよね。
反射的に「保険金請求と言えば、診断書を用意しなきゃ」と思う方もいるかもしれませんが、実は診断書がなくても、領収書などで請求できるケースが増えています。
スムーズに、損することなく保険金を請求するには、事前に保険会社に必要書類などを確認しておけば間違いありません。
保険会社で10年以上、支払査定をしてきた筆者が、保険金を請求するにあたって本当に診断書が必要なケースとその理由や、診断書のもらい方、実体験に基づくアドバイスなどを解説します。
この記事を読めば、効率よく保険金を受け取る方法が分かりますので参考にしてください。
医療保険の請求に必要な書類とは?【基本をわかりやすく解説】


保険金の請求においては、保険会社が治療内容などを把握するため、基本的に医師が証明した診断書が必要となりますが、条件を満たせば領収書などで手続きすることも可能です。
領収書などで請求できる条件や、その他に求められる書類も保険会社によって異なりますが、「医療機関で発行された書類」は確実に必要となるので、少なくとも領収書や診療明細書は準備しておきましょう。
診断書とは何か?なぜ求められるのか
診断書について改めて考えてみます。
具体的には、診断書には以下の内容などが記載されています。
- 治療を受けることになった病気の名前(傷病名)
- いつから病気が発症したか
- 経過
- 入院期間
- 実施した手術の名前および手術日など
保険金を受け取るには、基本的には「医療機関で発行される診断書が必要」と、各保険会社のHPには記載されています。
保険会社が診断書の提出を求めている理由は、契約している約款と照らし合わせて、支払条件を満たしているか判断するためです。



実際に治療を受けた事実を確認し、証明書上に治療内容や入院日数などの記載があることを確認して審査しています。
しかしながら現在では、特定の条件を満たす場合に診断書の提出を省略し、診療明細書や領収書、被保険者自身の報告書などで請求できる「簡易請求」を導入しています。
基本的には保険金請求において診断書は必要とされているものの、条件を満たせば診断書を取得することなく領収書等で請求ができるため、手間や費用がかからず、余計なストレスを減らすことができます。
よく使われるその他の提出書類
診断書があれば治療内容などが一目で確認できるため、基本的に他に必要となる医療機関発行の証明書類はありません。
ただし稀に、診断書の内容・情報を補完するものとして、領収書や診療明細書などが求められることもあります。
領収書や診療明細書は必ず交付され、条件があえば簡易請求に使用できることもあるため、大事に保管しておきましょう。
保険金請求においては、医療機関発行の書類の他に、本人確認書類など(請求を他の誰かに依頼する場合は「委任状」など)が必要となるため、運転免許証やマイナンバーカードなども準備しておきましょう。
診断書が必要な場合・不要な場合【実例で比較】
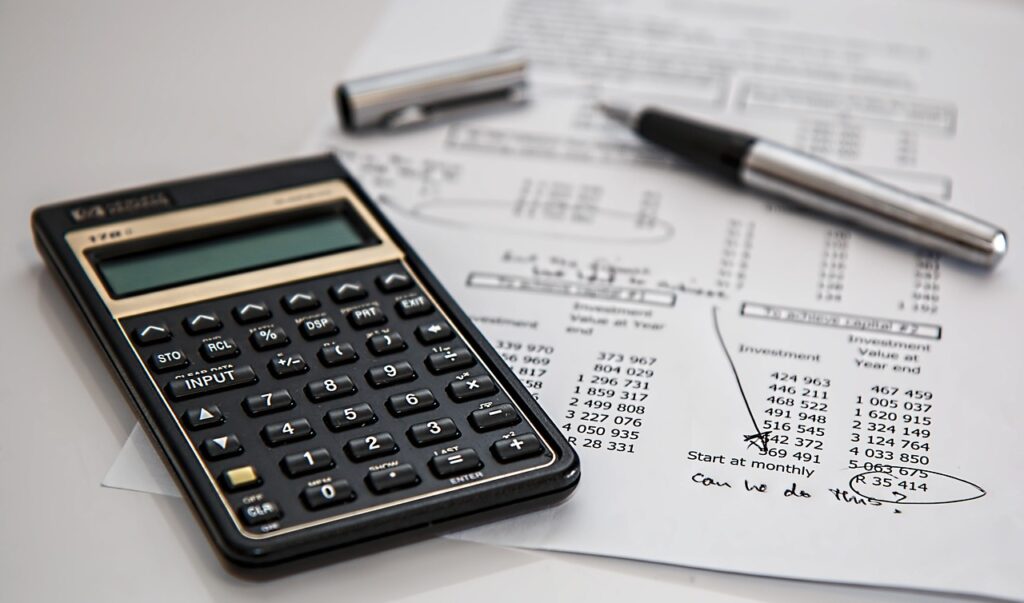
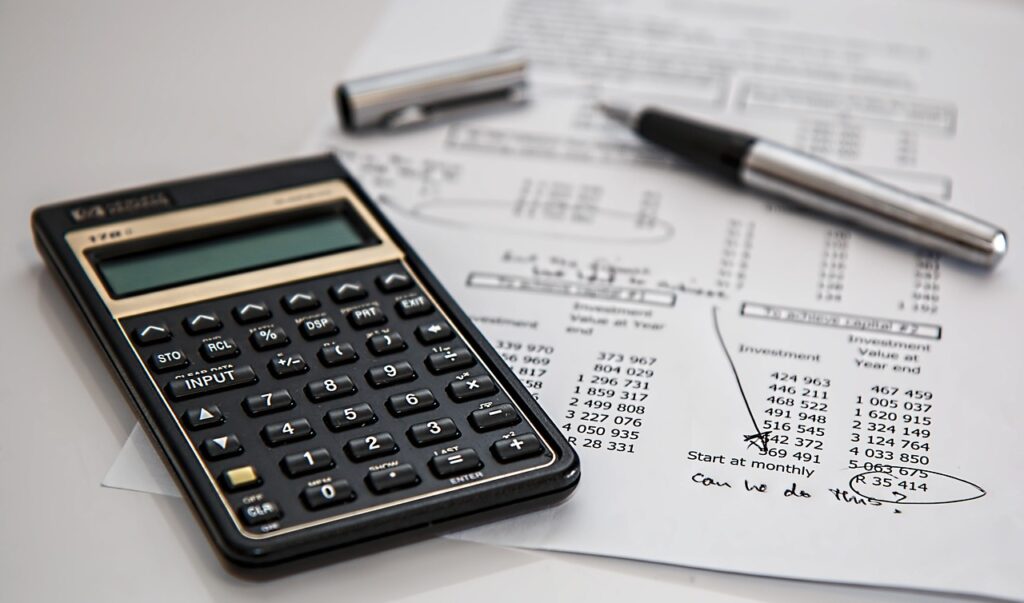
保険会社が診断書を確認する目的の一つに、お客さま(契約関係者)へ正確・迅速に保険金をお支払いするためという理由があります。
領収書などから得られる治療内容の情報は限られているため、正確な審査が必要なお客さまには診断書の提出を求めているのです。
どのようなケースで診断書が必須となるかか、また逆に診断書が不要なケースはどのような場合か、他にも保険金査定者はどのような目線で審査しているのかを紹介します。
診断書が必須となるケースとは?
保険会社が治療内容について詳細に把握する必要があるときは診断書の提出が必要となります。
具体的には、保険加入から2年以内の入院の場合は診断書が必要など、保険会社毎に一定の基準を設けています。
保険に加入して間もなく入院してしまったケースは「契約者が保険金を騙し取るために保険に加入したのではないか」という疑いがあるため慎重な審査が必要だからです。
保険に加入するにあたって過去の病歴について嘘をついていることが疑われるケース(告知義務違反)などは、治療内容やいつから病気が発症したかなど詳細に知る必要があるため、診断書が必要となるのです。
保険金を騙し取る目的で加入した人をそのままにしておくと、保険会社としては今後も保険金を多く支払うことになるかもしれず、保険金の原資となる保険料を、加入者からより徴収することになってしまいます。



悪意のある契約者を排除しておかないと、その他多くの普通の契約者が損をすることになるため絶対に許すことはできないのです。
その他にも、入院や手術保険金の請求ではなく、重度障がい状態(手足が不自由や目が見えないなど、日常生活に支障をきたす状態のこと)に該当するかどうかなどは、領収書等では判断できないため、専用の診断書が必要になります。
領収書や明細書で代替できるケースの具体例
基本的に、入院や手術保険金などの請求の場合は、必要な情報が領収書や診療明細書から確認できるため、保険会社の要件に当てはまれば領収書などが診断書の代替となります。
要件については保険会社のHPを事前に確認する。もしくは分からなければ、自分の場合はどうなのか直接保険会社に問い合わせてみましょう。
診断書ではなく領収書や明細書で請求するメリット
領収書や明細書で請求するメリットは大きく2つあります。
- 診断書の準備がいらないため、領収書などで早く請求でき保険金を受け取れる
- 診断書を取得する手間や費用も減らすことができる
10年ほど前は、正確な審査をするために診断書が必要という考えが一般的でした。
しかし現在は領収書などの情報でも信憑性が担保できると判断され、かつ請求手続きを簡素化した方がお客さまのためになると考える保険会社が多くなりました。
早まって診断書を取得する前に、保険金請求に診断書は必要か事前に保険会社に確認するとよいでしょう。
保険会社側の判断基準と傾向(査定現場の視点から)
保険会社は基本的に、提出された医療機関発行の証明書類(領収書や診療明細書も含む)を正しいものとして審査します。
領収書とお客さまの請求(申請)している内容に齟齬がないか、また契約している保険の保障内容に合致しているかを確認しているのです
たとえば、以下のような前提の場合の審査の観点を紹介します。
- ・保険の保障内容
-
加入から2年以上経過している
入院保険金は入院1日から保障する
手術保険金は約款の規定により支払ないものもある
- ・お客さまの請求内容
-
病名:大腸ポリープ
入院期間:2025.4.1~2025.4.3
手術日:2025.4.1
- ・領収書に記載の内容
-
診療期間:2025.4.1~2025.4.3
手術名:大腸ポリープ切除術
- 入院および手術は実施しているか(領収書の内容を確認)
- お客さまの請求している入院期間と医療機関が証明している(領収書など)期間に相違はないか
- いつ、どのような手術を実施しているか(診療明細書の確認)
- 契約している保険の保障内容に当てはまるか
→ 今回の場合、お客さまの請求内容と領収書などを確認すると、入院と手術の内容について疑義はない。
契約している保険の内容と照らし合わせて見ても、保障対象と分かるので保険金の支払対象と判断できる。
【診断書が必要な場合】医療機関で診断書をもらう流れと注意点


診断書が必要な場合、「どうやって病院に診断書を依頼するの?」と不安に感じる方もいるのではないでしょうか。
診断書の取得には費用も時間もかかるため、事前に流れと注意点を押さえておくことが大切です。
ここでは、受付での伝え方から受け取りまでの流れ、よくある失敗例とその対策までを詳しく解説します。
受付での伝え方と依頼の手順
診断書の取得は、基本的には医療機関の受付窓口で申し出る形になります。
以下のように伝えればスムーズです。
「医療保険の給付金請求のために、診断書をお願いしたいのですが。」
もし保険会社から指定の診断書フォーマットがある場合は、その書式を印刷して持参しましょう。
保険会社によっては独自の様式を用意しているため、事前に確認が必要です。
指定がなければ、医療機関の汎用フォーマットで発行されます。
依頼後は、以下のような流れが一般的です。
- 受付で診断書の依頼
- 担当医師が記載(通常、診察の合間に対応)
- 完成後、文書窓口で連絡が来る/受け取り
注意点として、当日発行はほぼ不可能なので、時間に余裕を持って依頼することが重要です。
費用相場と発行までの期間
診断書の発行には費用がかかります。以下が一般的な目安となります。
- 費用相場:3,000〜10,000円程度(病院や書式の内容により異なる)
- 発行期間:通常1〜2週間ほど(混雑状況や医師のスケジュールにより前後)
なお、費用は医療保険の補償対象外であり、自己負担になります。
発行後は現金払いのケースが多いですが、病院によっては先払い(前金)を求められることもあります。
診断書の内容を確認して損を防ぐ
診断書が完成しても、受け取ってすぐ保険会社に提出するのでなく内容を確認しましょう。



自分に責任は無くても、病院側で記載ミスや漏れがあると、保険会社からの再提出依頼や支払い遅延の原因になってしまいます。
特に以下の項目は、しっかり確認しましょう。
- 病名・傷病名が明記されているか
- 入院・通院・手術の実施日が正確か
- 発行元である医療機関名称および医師氏名の記載があるか
仮に記載誤りや漏れがあった場合でも、保険会社によって対応は異なりますが、発行元の医療機関に保険会社が電話で確認して問題が解決することもあります。
しかし一方で、医師の証明が漏れているケースなどは、そもそも診断書の偽装が疑われてしまうので、電話ではなく再度記載を求めることになります。特に証明欄は注意して確認した方がよいです。
診断書が取れないときの保険金請求方法【事実確認とは?】


診断書は取得できる期限が決まっています。
何年も前の場合、医療機関はカルテの保存期間の関係があるため、医療機関の都合で診断書が取得できないということもあります。
ではその場合、もう保険金の請求はできないということになるのでしょうか。
実際はそんなことはなく、保険会社は病院に調査(事実確認)を行うなどして、何とか審査をしようと試みます。
診断書が提出できなくても諦めることなく、可能な限り治療内容を証明する書類を探して提出することで、保険会社が審査できる可能性があるのです。
保存期間終了・病院閉鎖時の対応方法
一般的に医療機関のカルテの保存期間は通常5年〜10年となっています。
数年前の入院や手術にかかる保険金を請求しようとする場合、病院側がデータを持っていないことも想定され、保存期間が経過していると事実上診断書の取得は不可能です。
この場合、診断書取得を断念するしかなく、自身で当時の病院発行の領収書などが残っていないか探すしかありません。



病院側の都合によりますが、なんとか対応してくれるかもしれません。
保険会社による「事実確認支払い」の実際
診断書がない場合、保険会社はそれだけで支払いを拒否するかというと、そんなことはありません。
足りない情報は、医療機関へ調査(事実確認)を行い、情報を補完することもあります。
調査(事実確認)を要する場合には、必ず請求人本人の同意が必要ですので、(医療機関が本人の同意なしに情報を開示することはできないからです。)保険会社が委託している調査会社から連絡があります。



最初は、調査と聞くと驚くかもしれませんが、公正な保険金の審査を行うためですので、同意を求められた際はきちんと説明を聞いて対応しましょう。
必要になる代替資料と記録のポイント
診断書の取得が不可能な場合、代わりになる可能性がある書類を紹介します。
領収書や診療明細書は、治療が終わった際に発行される書類なので、治療の事実を証明する書類としてとても有用です。
その他、治療前に医療機関から渡される治療計画書や、手術の事前説明書なども、治療したことを証明するものではないものの、審査の参考情報になり得ます。
薬局のレシートや、自身で記録したメモなどが役立つこともあるかもしれません。



いずれにしても、診断書の取得ができない場合は、何でもよいので可能な限り治療に関わる書類を提出するしかありません。
自分にできることを全てやって、あとは提出された書類をもとに、どのように審査するか保険会社の判断に委ねましょう。
保険金請求をスムーズに進めるコツ【査定経験から学ぶ】
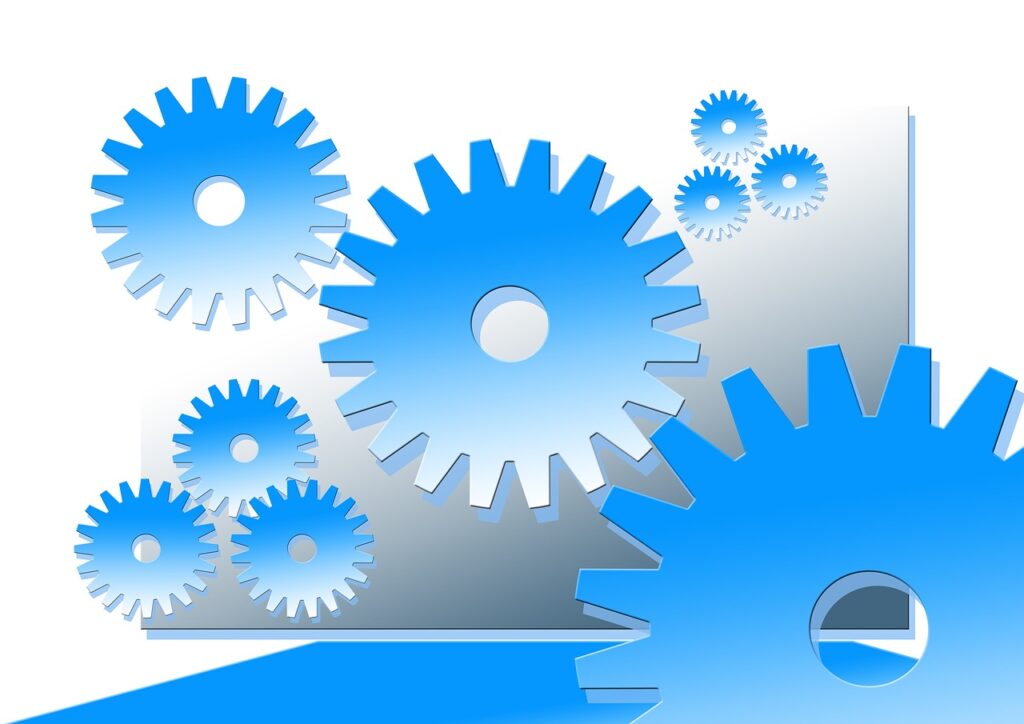
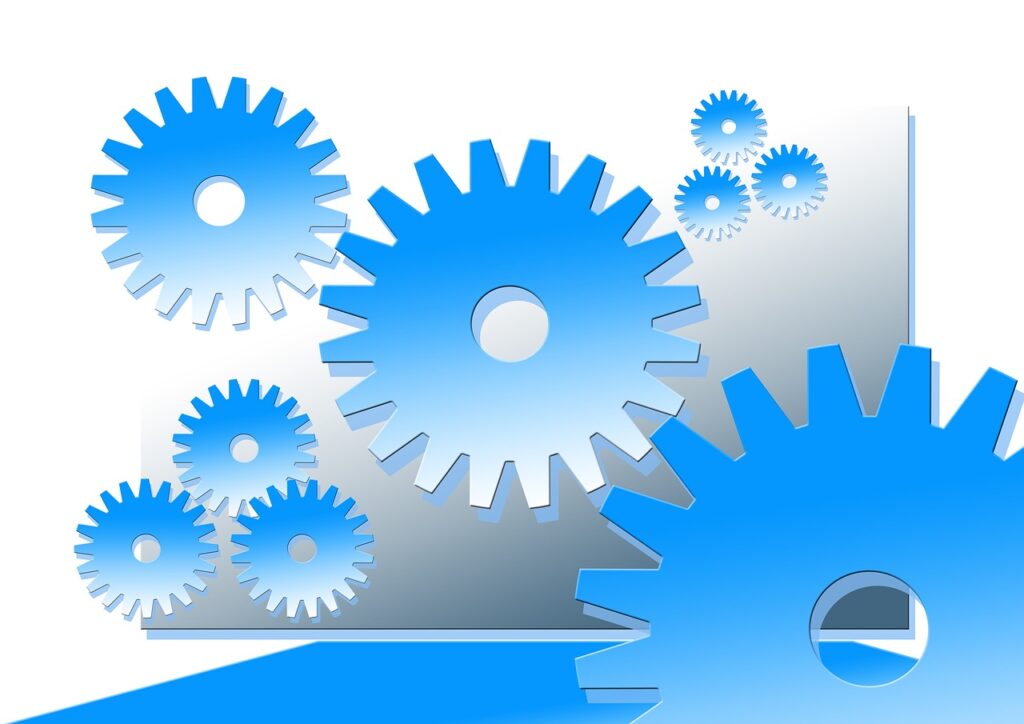
保険金の請求は、「書類を出せば終わり」ではありません。
実際には、不備・記載漏れ・確認不足などが原因で、支払いが遅れたり、請求自体が通らなかったりするケースも多くあります。
ここでは、10年以上の支払査定経験をもとに、スムーズに、かつ確実に保険金を受け取るためのポイントをお伝えします。
事前準備で差がつく!確認すべきこと
まず大切なのが、「何を提出する必要があるのか」を事前に把握することです。
- 自分の契約内容を確認する(入院・手術・通院などの給付対象や日額)
- 必要書類一覧を保険会社に確認する
- あわせて診断書が必要かどうかも先に聞いておく
契約内容と異なる申請をしてしまうと、「対象外で不支給」となることもあります。
書類を用意する前に、保険会社に一度電話をして確認するのがベストです。
問い合わせで聞くべき質問リスト
問い合わせ時には、以下のようなポイントを事前にメモしておくとスムーズです。
- 「診断書は絶対必要ですか?」
- 「領収書や明細だけで請求できる可能性はありますか?」
- (診断書が必要な場合)「フォーマットはありますか?病院の書式でも大丈夫ですか?」
- 「書類はコピー提出でよいですか?原本が必要ですか?」
保険会社側は、提出してもらった書類で判断するしかないため、初期段階のすり合わせが極めて重要です。
実体験からの3つのアドバイスと注意点


実際に保険金査定業務を10年以上経験してきて、特にアドバイスしたいのは以下の3点です。
領収書などで請求できるのであれば、診断書は不要
この10年ほどの間に、各保険会社とも保険金の請求方法がかなり簡単になりました。
仮に診断書が不要にも関わらず、手間と時間とお金をかけて診断書を取得しても、お客さま側にメリットはありません。
しかし事実として、領収書の提出で足りるものを、わざわざ診断書を取得して請求してしまうお客さまは少なからず存在します。
損をしないように、きちんと事前に必要書類は保険会社に確認するようにしましょう。
手続き関係で特に多いのが記載ミス・漏れ
現在では診断書の提出よりも、領収書などで請求できるケースがかなり増え、必要書類も簡素化されましたが、それでもなくならないのが記載ミスです。
領収書などで請求する際は、請求人が何の病気で入院などしたかを自分で申告しなければなりません。
また他にも、自分で入院した期間や手術をした日を申告するケースがあります。
その申告する内容が、領収書などの情報と相違している場合、確認が必要となってしまい、審査を進めることができなくなってしまいます。
保険金を請求する際、自身で記載・申告する内容に誤りがないかよくチェックしましょう。
請求人の確認書類での不備もある
領収書などの医療機関の発行の書類の他に、保険金請求の手続きでは本人確認書類などが必要です。
入院した本人が請求するのであれば、多くの場合問題ありませんが、請求を家族に依頼(委任や代書)する場合は別途委任状などの書類が必要となり、自身で記載して提出する書類が増えます。
領収書などだけではなく、請求人に関する書類も不備があると受け付けられませんので、十分に確認の上手続きする必要があります。
まとめ|診断書にこだわらず、柔軟に請求しよう


医療保険の請求というと、「まず診断書をもらわなきゃ」と思い込んでしまいがちです。
しかし実際には、診断書がなくても保険金を請求できるケースが多く存在します。
保険会社では、領収書や診療明細書からでも必要な情報が読み取れる場合には、診断書の提出を求めずに支払いを行う「簡易請求」が主流になりつつあります。
これは、お客さまの手間や費用を減らし、より迅速に保険金をお届けするための仕組みです。
もちろん、場合によっては診断書が必要なケースもありますが、診断書が必要かどうかの判断は、保険会社ごと・契約内容ごとに異なるため、事前に問い合わせて確認することが何よりも重要です。
10年以上支払査定に携わってきた立場からお伝えしたいのは、焦って行動せずに、せっかくの保険金請求で損をしないためにも、正しい情報を得て、必要な書類を見極めて、柔軟に対応することです。
あなたの大切なお金ですので、少しだけ丁寧に準備して、スムーズに、そして確実に保険金を受け取りましょう。

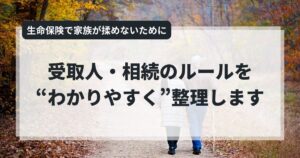
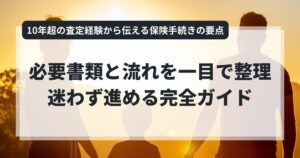
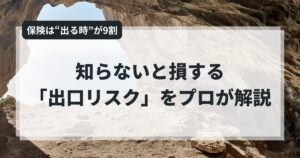
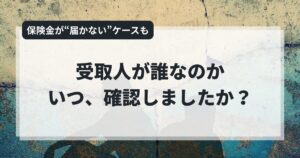
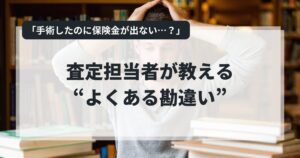
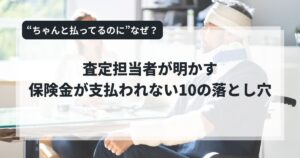
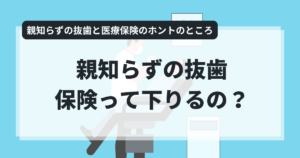
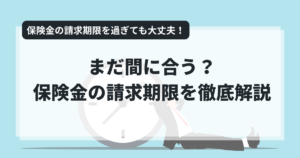
コメント